原作はロシアの無名の俳優セルゲイ・フェティソフによる回顧録「ロマンについての物語」。
監督はペーテル・レバネ。ミュージック・ビデオなどで活躍していた人とのこと。
主演は『博士と彼女のセオリー』などのトム・プライヤー。
物語
1970年代後期、ソ連占領下のエストニア。モスクワで役者になることを夢見る若き二等兵セルゲイ(トム・プライヤー)は、間もなく兵役を終える日を迎えようとしていた。そんなある日、パイロット将校のロマン(オレグ・ザゴロドニー)が、セルゲイと同じ基地に配属されてくる。セルゲイは、ロマンの毅然としていて謎めいた雰囲気に一瞬で心奪われる。ロマンも、セルゲイと目が合ったその瞬間から、体に閃光が走るのを感じていた。写真という共通の趣味を持つ二人の友情が、愛へと変わるのに多くの時間を必要としなかった。しかし当時のソビエトでは同性愛はタブーで、発覚すれば厳罰に処された。一方、同僚の女性将校ルイーザ(ダイアナ・ポザルスカヤ)もまた、ロマンに思いを寄せていた。そんな折、セルゲイとロマンの関係を怪しむクズネツォフ大佐は、二人の身辺調査を始めるのだった。
(公式サイトより抜粋)
ソ連における同性愛
本作の舞台は1970年代で、エストニアはまだソ連の一部ということになる。主人公のセルゲイ(トム・プライヤー)もソ連軍の一員として働いている。パイロットの話ということで『トップガン』の同性愛バージョンみたいなものを勝手に想像してしまっていたのだが、実際に戦闘機が登場する場面はそれほどはない。これは単に予算の関係なのかもしれない。戦闘機を飛ばすことはかなり金のかかることなのだろうから。ちなみにタイトルの「ファイアバード」も戦闘機の名前というわけではなく、『火の鳥』という演劇から採られているものだ。
最初の舞台となるのは軍隊内部だ。セルゲイはそこで上官として赴任してくるロマン(オレグ・ザゴロドニー)と出会い、惹かれ合うことになる。ただ、そこには障害がある。たとえばイスラム圏を舞台にした『青いカフタンの仕立て屋』では同性愛自体が禁固刑とされていたわけだけれど、ソ連においてもそれは同様だ。
ソ連においても刑法121条というものによって同性愛が禁止されていたらしい。その理由が何なのかはよくわからない。宗教的なものなのかもしれないけれど、本作にはほとんど宗教に関する描写はないわけで、共産主義の思想において禁止されているということなのかもしれない。
とにかく当時のソ連においては、同性愛がバレてしまえば刑法に違反することになり処罰を受けることになる。そのためセルゲイとロマンはKGBであるズべレフ少佐(マルゴス・プランゲル)から目を付けられることになってしまうのだ。

© FIREBIRD PRODUCTION LIMITED MMXXI. ALL RIGHTS RESERVED. / ReallyLikeFilms 2023
国を動かした映画
公式サイトの記載によれば、本作はエストニアで初めて公開されたLGBTQを題材とした映画だったらしい。そんなこともあってか本作はエストニアでは大ヒットすることになり、エストニアで同性婚が承認されることになるひとつのきっかけとなったとのこと。これは旧ソ連圏では初めてのことであり、映画が国を動かしたとも言えるのだろう。
本作がどれほどの影響力があったのかは公式サイトの記載だけではわからないけれど、本作がエストニアで初めて公開された同性愛を題材にした作品だったことは大きいのだろうし、監督であるペーテル・レバネはもともと同性愛者の結婚に関するロビー活動などもしていたようなので、そうした活動の成果もあるのだろう。
確かに『Firebird ファイアバード』を観れば、同性愛を禁止する法律なんかなければよかったのにといった気持ちを抱くことになるだろう。それでもソ連時代はそんな法律が存在し、それによって国民は縛られることになっていたのだ。
※ 以下、ネタバレもあり!

© FIREBIRD PRODUCTION LIMITED MMXXI. ALL RIGHTS RESERVED. / ReallyLikeFilms 2023
ふたつの三角関係
本作ではふたつの三角関係が描かれている。最初はセルゲイとその親友の男とルイーザ(ダイアナ・ポザルスカヤ)だ。この時の描写を観ていると、ルイーザはセルゲイのことを気に入っていたのだろう。それでもセルゲイ自身は自分がゲイであることを認識していて、彼女からのアプローチをうまくかわしていたということだろう。親友の男はセルゲイにルイーザとのことを問い質してもいたのだが、セルゲイはルイーザのことを「妹みたいな存在」などと言って誤魔化すことになる。
その後にロマンが基地に赴任してくることになる。それによって状況が変化することになり、新たな三角関係が形成されることになる。ルイーザは煮え切らないセルゲイを諦めてロマンに向かったのだ。しかしそのロマンも実はゲイであり、ロマンの気持ちはその部下として配属されることになったセルゲイのほうへと向かうことになってしまう。
三角関係の場合は誰かがそこから弾き出されることになる。最初の三角関係の場合は、弾き出されたのは親友の男とも言えるけれど、そもそもセルゲイにはそんな気持ちはなかったわけで三角関係に見えても、そうではなかっただけということになる。それに対して、次に形成される三角関係ではさらに問題が生じることになる。
セルゲイとロマンはすぐに惹かれ合い愛し合うようになる。ここで弾き出されるのはルイーザということになる。それで事が済めば、ルイーザが失恋しただけで済んだだろう。容姿端麗で魅力的なルイーザだけに、すぐに次の相手を見つけたかもしれない。
ところがソ連では同性愛は禁止されているわけで、ロマンとしては自分の身とセルゲイのことを守るためにもセルゲイのことを突き放すしかない。そして、世間の目を欺くためにも結婚する必要が生じることになり、ロマンが選んだのはルイーザだったということになる。

© FIREBIRD PRODUCTION LIMITED MMXXI. ALL RIGHTS RESERVED. / ReallyLikeFilms 2023
一番の被害者は?
エンドロール後に仄めかされているように、裏でKGBが暗躍していたことがセルゲイとロマンを引き離すことになったのだろう。もちろんこのことは悲劇なのだけれど、それだけでは終わらない。ロマンがした選択が秘密のままで終わればよかったのかもしれないけれど、最終的にはすべてが明らかになってしまうのだ。そうなると何も知らなかったルイーザが一番の被害者にも見えてしまう。
本作は実話なのだそうで、原作者の方は映画が完成する前に亡くなってしまったようだが、その原作は「ロマンについての物語」と名付けられている。セルゲイのロマンに対する愛情というものが描かれていたのだろうか。そのあたりはよくわからないけれど、劇中の台詞「私の愛は、あなたたちの愛に決して劣らない」というところに力点が置かれているのかもしれない。
ただ、それが語られる相手がルイーザということもあって、ちょっと微妙な感じもしてしまった。「同性愛が異性愛に劣らない」というのはわかるけれど、それを一番の被害者とも言える、何も知らずに巻き込まれた形のルイーザに向かって言うべきことなのかとも感じてしまったのだ。
このシーンでは自分たちの愛に胸を張るセルゲイのほうに原作者の力点はあったのかもしれないけれど、観る側としてはルイーザのほうに同情してしまう気もして複雑だったのだ(自分たちの行動によって傷つけた人もきちんと描く原作者は正直者なのだろう)。ルイーザは二度とセルゲイと会わなかったというのだが、その怒りも「さもありなん」という気もする。
とはいえ理不尽な法律に振り回される被害者がいたからこそ、この映画がエストニアで同性婚を認めさせるほどの説得力を持つことになったのかもしれないけれど……。
本作はエストニアでは珍しかったのかもしれないけれど、日本などでは最近はLGBTQを描いた作品は決して珍しくはない。本作は障害のある恋愛という意味では典型的とも言える感じもして、ほかの多くのゲイムービーとの違いといったものはあまり感じられなかった気もする。尤も、主役の3人は美男美女ということで眼福ではあるのだけれど……。



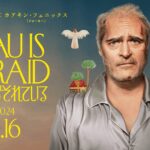

コメント