監督・脚本は『心と体と』などのイルディコー・エニェディ。
原作はミラン・フストの小説。
原題は「A feleségem története」で、これを英語に翻訳すれば「The Story of My Wife」ということらしい。
物語
1920年のマルタ共和国。
船長のヤコブ(ハイス・ナバー)は、
カフェに最初に入ってきた女性と結婚するという賭けを友人とする。
そこにリジー(レア・セドゥ)という美しい女性が入ってくる。
ヤコブは初対面のリジーに結婚を申し込む。
その週末、二人だけの結婚の儀式を行う。
幸せなひと時を過ごしていたが、
リジーの友人デダン(ルイ・ガレル)の登場により
ヤコブは二人の仲を怪しみ嫉妬を覚えるようになる…。
(公式サイトより抜粋)
タイトルに偽りあり?
タイトルを日本語にすれば「私の妻の物語」ということになるが、これはその中身とはちょっと異なる。たしかに夫から見た妻の姿が描かれることになるわけだけれど、その妻は謎めいた女性であり、彼女の内面が明かされることはなく、内実としては妻に翻弄される夫(つまり私)の物語となっているのだ。また、タイトルには「船乗りヤコブと7つの教訓」という副題も示されており、本作は7つのチャプターに分かれて展開していく。
海の男であるヤコブ(ハイス・ナバー)が妻を娶ろうと考えたのは、自分の身体のことを考えたからだ。3人の妻を持つという料理長の男が健康のために結婚することを勧め、ヤコブはその言葉にあっさりと乗ることになる。
ヤコブはある日、悪友コードー(セルジオ・ルビーニ)と会った時に、思いつきのように「最初に店内に入ってきた女性と結婚する」という賭けをする。そして、その時現れたのがリジー(レア・セドゥ)だったのだ。
ヤコブはリジーに唐突に結婚を申し込むことになる。もしもリジーがごく一般的な女性だったとしたら、そんなプロポーズは受け入れられないだろう。ところがリジーはその申し出を受け入れる。「奇妙な企みに加担してあげるわ」とでもいうような笑みを浮かべて……。

(C)2021 Inforg M&M Film Komplizen Film Palosanto Films Pyramide Productions RAI Cinema ARTE France Cinéma WDR/Arte
何を描いた映画なのか
『ストーリー・オブ・マイ・ワイフ』は、ヤコブとリジーの結婚生活を描くことになるわけだが、169分という長尺で一体何を言わんとしているのかということについては、正直よくわからなかった(だから以下の文章も勝手な解釈に過ぎない)。
リジーとは一体何者なのか。私は先に「謎めいた女性」と記したのだが、本作の監督イルディコー・エニェディや、レジーを演じているレア・セドゥとしてはそれを狙っていないという。複雑ではあるけれど、謎めいているわけではないということらしい。
監督が公式サイトにアップしている「Director’s Note」では、リジーのことを「しっかりと閉じられたエレガントで素敵な小箱」にたとえている。しかしヤコブはその箱を開けることができない。リジーは見た目は麗しく魅力的だが、その内心に何を抱えているのかわからない。ヤコブはそんなリジーに翻弄されることになる。
本作においては、最後までリジーの内面が明かされることはない。前半部では、警察がリジーの正体を知っていることを仄めかしている。警察は英語しかしゃべれないヤコブが、マルタ共和国という外国で哀れな状況に陥りそうなのに同情し、ヤコブに何かしらの助言を与えたのだろうと推測される。ヤコブは警察からリジーの話を聞いたはずだ。それでもあえてリジーと結婚することをやめなかったということになる。
後半では、リジーが友人のデダン(ルイ・ガレル)と一緒にヤコブの株券を持って逃走するところをヤコブに押さえられ、リジーは離婚に必要な文書を書かされることになる。ここからすればリジーは金持ちをカモにする詐欺師みたいなものだったのかもしれないのだが、それも曖昧なままに留まっている。結局、本作はヤコブとリジーの結婚の失敗を描いただけのようにも見える。かといってラブストーリーなのかと言うとそうでもないような気もして、意図が測りかねる気がしたのだ。

(C)2021 Inforg M&M Film Komplizen Film Palosanto Films Pyramide Productions RAI Cinema ARTE France Cinéma WDR/Arte
息子へのメッセージ
本作はヤコブの“語り”から始まる。それはすべてが終わった後に語られるものであり、ラストの“語り”は冒頭とつながっている。ヤコブはリジーとの関係を振り返って、そんな言葉を漏らしているということになる。
その“語り”では、ヤコブは「自分に息子がいたとしたら」と仮定している。自分の分身のような息子に対し、人生という大海原を生き抜くための羅針盤になるような言葉が語られることになる。ここで語られる言葉は悲観的なものだと言える。
ヤコブはリジーとの関係で疑心暗鬼になっていた頃、川に身を投げて自殺を図ることになるのだが、それに失敗し、医者に諭されることになる。その時に医者が語っていたことが印象的だ。その医者はわれわれは殺される前に泣き喚く子豚みたいなものだという。この世界はわれわれのものではなく、われわれは部外者でしかない。だからわれわれの魂が救われることはない。医者はそんなふうに語る。これは先ほどの“語り”とも結びつくエピソードだろう。

(C)2021 Inforg M&M Film Komplizen Film Palosanto Films Pyramide Productions RAI Cinema ARTE France Cinéma WDR/Arte
哀れな子豚
また、本作の冒頭と最後におけるヤコブの“語り”の部分では、海の中のクジラの姿が描かれている。クジラは本作の物語とはまったく関わりがないのだが、なぜか海の中のクジラが登場する。これは単純に監督のイルディコー・エニェディが動物が好きだからなのだろうと思う(ほかにも甲板で猫がひょっこりと顔を出すシーンもある)。イルディコー・エニェディの処女作『私の20世紀』ではチンパンジーが登場していたし、前作の『心と体と』でも動物が印象的に使われていたりもする。
その『心と体と』では、夢の中で鹿のつがいの姿が描かれる一方で、現実世界で主人公が働いているのは食肉加工工場だった。そして、劇中では実際の食肉加工工場で撮影された牛の屠殺シーンがあった。牛は何が起きるのか知らないまま機械的な処置によって一瞬にして殺され、頭を斬り落とされ、肉に加工されていく。
このシーンは、本作で医者が語る子豚の姿と重なるものなんじゃないだろうか。牛は子豚のように泣き喚くわけではないけれど、この世界の部外者であることは一緒だろう。われわれ人間は子豚や牛を屠る側にいる。しかしながら、世界の部外者であるという点では、われわれも動物たちと何も変わらない。
子豚や牛はわけもわからずこの世界に産み落とされ、わけもわからないうちに殺されていく。それと同じようにわれわれ人間も、人生の意味というものもわからないうちに呆気なく死んでいくことになる(リジーはヤコブと別れてすぐに亡くなったらしい)。ヤコブが架空の息子に伝えようとしていたのは、そんな悲観的な認識だったんじゃないだろうか。
ヤコブにとってリジーとの結婚生活というものは、単なる愛とかセックスなどの問題ではなく、ヤコブの人生を賭けたものだったということなのだろう。リジーとの結婚がうまく行けば、人生には価値がある。ヤコブが自ら「賭けをしよう」と言い出したのは、そういう意味だったんじゃないだろうか。
その意味ではヤコブはその賭けに負けたのかもしれない。リジーと結婚できたといはいえ、それは失敗に終わることになったわけだから。その虚しさが悲観的なメッセージとなり、「あがいたところでどうにもならない」といった諦念につながっているのではないか。
本作は169分の時間をかけヤコブの結婚の失敗を描いているわけだが、レア・セドゥはリジーを魅力的に演じているとはいえ、リジーの内面は一切明かされないわけで、後半は間延びしたものを感じたし、前作『心と体と』がとてもよかったので本作にも大いに期待していたということもあって余計にガッカリ感を味わった。
もっともこれはヤコブの結婚生活が大いなるガッカリに終わったことと同じなのかもしれない。人生において何に賭けるべきなのかはわからないけれど、本作の認識では何に賭けても結果は一緒ということだろうか? タンゴを踊るシーンはよかったし、甘美なベッドシーンもあったりもするのだけれど、終わってみればすべてが物悲しいものにも感じられる。そんな映画だったような気がする。

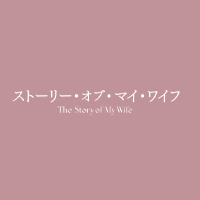





コメント