実際に起きた事件をモデルとしたフィクション。
事件に関しては、『誰もボクを見ていない:なぜ17歳の少年は、祖父母を殺害したのか』というノンフィクションが出版されている。
物語
真っ当に仕事をすることもなく、周囲から金をせびり自堕落な生活をしている秋子(長澤まさみ)。秋子には周平(郡司翔/奥平太兼)という息子がいるのだが、学校に行かせることもなく自分の都合よくこき使っている。周平はそんな母親から離れることもできず、ただ秋子に言われるがままに生きていくことになり……。
理解できない人物像
主人公である秋子は常識的な観客からしたらまったく理解できない人物だろう。真面目に働いて稼いでいる者をバカにするように借金を重ね、当然の如くそれを返すつもりもないからだ。「働かざる者食うべからず」という慣用句など聞いたこともないかのような生き方なのだ。
何か恨みでもあるかのように社会のルールから逸脱していく秋子は、それを息子の周平にも学ばせようとする。飛び込み禁止のプールでわざわざ監視員の前で飛び込んでみせるシーンにもそれが表れているわけだが、秋子にとっては何らかの快感なのかもしれないが、周平には戸惑いのほうが大きい。
たとえば『俺たちに明日はない』の主人公のように破滅に向かって突き進んでいくならば何らかの美学を感じなくもないわけだが、本作の秋子にはそんなカッコよさはない。内縁の夫となる遼(阿部サダヲ)が金を脅し取ろうとした男を刺してしまった時は、慌てて田舎に身を隠すほどビビりでもある。逮捕されて自分の自由が奪われることが怖いのだ。秋子は狭い世界に閉じこもり、周平という自分の分身を利用して自堕落に生きることだけが望みで、それ以上の展望は何もないのだ。

(C)2020「MOTHER」製作委員会
ネグレクトか犯罪強要か
本作は17歳の少年がその祖父母を殺害した事件をモデルとしている。同じように親からの虐待を描いた作品ということで言えば『誰も知らない』(是枝裕和監督)がある。『誰も知らない』では、母親は子供たちの存在を忘れたかのように消えてしまう。これによって命を落とす子供も出たわけで、このケースも酷い話であることは確かだが、『MOTHER マザー』のケースもそれに負けてはいない。
『MOTHER マザー』の秋子の場合も、一度は遼と長く自宅を留守にすることに。その間は一応世話人を用意してはいるわけだが、電気もガスも止まってしまった自宅では、周平は母親がいなくなってしまうことの恐怖を植え付けられることになってしまう。このことが周平が秋子から逃れられなくなる要因ともなっている。
それをいいことに秋子は周平を好き勝手に利用することになっていく。また遼との間に妹も生まれ、妹を守るためにも周平はますます秋子から離れられなくなっていく。次第にエスカレートしていく秋子の要求は犯罪すら厭わなくなり、最終的には祖父母を殺害するという結末を迎えることになってしまうのだ。

(C)2020「MOTHER」製作委員会
塀のなかは楽園?
事件後、実行犯である周平は逮捕されることになるわけだが、弁護士などの意見にも関わらず、周平は事件を単独の犯行であると供述する。母親を庇って自分だけが罪をかぶるのだ。そのおかげもあって秋子は執行猶予付きの判決で済むことになる。
秋子は開き直って「周平はわたしの子供だから、どんなふうに育てようがわたしの勝手」と言い張ることになるわけだが、こんな言い草は誰も認めることはないだろうし、自由をはき違えているとしか思えない。一方で周平は懲役12年の刑も、三食付きの安心な場所が確保できたことになり、そのことに満足しているふうにすら見える。
通常の感覚ならば、自由というものは普遍的な価値であり、それは誰にとっても重要な意味を持つものだと考えるわけだが、周平にとってはそうではなかったということになる。というのも、周平は長年母親と妹という狭い世界しか知らず、物事を学ぶことをしてこなかったからだろう。教育というのは洗脳であるとも言うけれど、ある程度の教育がなければ、真っ当な考えにたどり着くことすら阻害されることになってしまうということだろう。

(C)2020「MOTHER」製作委員会
解釈しないという手法?
本作は「こんな悲惨な事件がありました」という実例報告としてあるのかもしれないのだが、観客としてはその報告を受けて戸惑うことになるかもしれない。というのは、タイトルロールである秋子に対してまったく共感することができないからだ。
秋子というモンスターの被害者である周平に関しては、丁寧に描いているとも言える。それが愛ではなくマインドコントロールだとしても、周平は事件後に「母親が好きだから」と告白することになり、その行動を理解できなくもないからだ。
しかし、そもそもの元凶であるマザー・秋子に関しては、謎のままに留まっているし、秋子が改悛するような素振りもない。観客としては周平に対しては秋子から逃げ出さないことのもどかしさを感じ、秋子に対してはまったく理解不能なままの不快感を抱えたまま終わることになる。本作ではこの重苦しいもやもやとした感情を解消すべき道筋がまったく見えないのだ。
福祉行政がもっと介入すべきであったのかもしれない。本作では亜矢(夏帆)というキャラがその役割を担っているわけだが、それも今一歩踏み込むこともできずに終わってしまう。しかし、本作ではそこを糾弾していこうという意図も感じられない。
監督・脚本の大森立嗣は、事件に対する解釈を忍ばせないことを大前提にしているのかもしれない。わからないものはわからないままにということだ。あとは観客が考えるべきことということなのかもしれないのだが、秋子を理解することを放棄しているようにも思えてしまった。





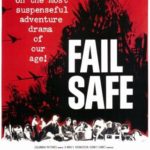

コメント