東京国際映画祭でコンペティション部門にノミネートされたジョージア(グルジア)映画。
監督はザザ・ハルヴァシ。本作は長編4作目とのこと。
原題は「Namme」。
物語
舞台はジョージアの南西部の山深い村。そこには聖なる泉があり、それを守り続けている一家がいた。年老いた父(アレコ・アバシゼ)がその儀礼を取り仕切っていたが、後継者となるはずのナーメ(マリスカ・ディアサミゼ)はもっと普通の生活がしたいと考えていた。
古くから伝わる物語
『聖なる泉の少女』の基になっているのは、ジョージアのアチャラ地域に古くから伝わっている物語とのこと。
「むかしむかし、泉の水で人々の傷を癒していた娘がいました。いつしか彼女は他の人々のように暮らしたいと願い、自らの力を厭うようになりました。そしてある日…」
本作では上記の物語に加え、泉のなかには白い魚がいるという設定。その泉は澄んだ水が湧いているのだが、あまりにも狭くて小さい。その白い魚は小さな泉のなかで一生を終えることになるわけだが、この魚は泉を守る家に縛られているナーメの姿そのものとも言えるのだ。
ナーメの三人の兄
ナーメには三人の兄がいるのだが、それぞれ独立してその家を離れてしまっている。ひとりはジョージア正教の神父となり、ひとりはイスラム教の聖職者、ひとりは無神論の科学者となっている。兄たちは聖なる泉の力を信じてはいないようだ。古くから伝わっている泉の力よりも、もっとほかの何かを信じているということらしい。
ちなみにジョージアという国は4世紀にすでにキリスト教を国教としたらしいのだが、隣はトルコということもあって6世紀にはイスラム帝国の支配下にあったこともあり、イスラム教の影響も残っているらしい。そして、近年はもちろん科学技術も流入してきている。三人の兄はジョージアという国のそのものということなのかもしれない。

(C)2017 BAFIS, UAB Tremora
幻想的な儀礼の様子
夜中にひっそりと行われる泉を守る儀礼がなかなか幻想的で、暗闇を照らす炎が超自然現象のように発生するあたりが印象的。そうした儀礼によって力が保たれている泉の水は、癒し手であるナーメによって心身を病む患者につけられると病が癒える効果がある。村人たちもそうした泉の力を信じていて、昔ながらの信仰の対象としてその泉は存在していることが見てとれる。
ただ、今ではそれを脅かすものがある。それは端的に言えば環境汚染ということになるだろう。三人の兄のひとりが科学者であったように、科学技術はジョージアの山奥にも押し寄せてくる。山の奥には水力発電所があり、それによって澄んでいた川の水も濁ってきたように、泉の水はいつの間にかに枯れることになってしまう。
美しい映像は堪能したのだが……
旧ソ連のグルジアという国が、今ではジョージアと呼ばれるようになった。そのくらいの知識しかないのだが、そんな国の作品を観る機会も滅多になさそうなので興味を持った。
古くから伝わる物語の映像化ということだが、それが伝承しようとしているものが何なのかは今一つわからなかった。普通の生活を望み、たまたま知りあった男性に惹かれたりもしているナーメは、最後に泉の主である魚を逃がし、ナーメ自身も白い靄のなかへと消えて行ってしまう。
この古い伝承は因習に縛られている女性の解放を伝えているということなのだろうか。三人の兄は古くから伝わる泉に対する信仰とは別のものを選び、ナーメもそれを捨てて自由に生きるほうを選んだとなれば、一体何が残るのかとも思うのだが……。そのあたりは台詞をほとんど排除し映像だけに語らせようとしているために、解釈によって様々ということになるのかもしれない。
魚が解放される場所は辛うじて残っていたのかもしれないのだが、ナーメがそうした因習から解放される場所はあったのだろうか。ラストに登場する山の上の湖の風景がとても美しく、そこをゆっくりと歩いていくナーメはキリストが水の上を歩く姿のようにも見えた。ナーメを演じるマリスカ・ディアサミゼのエキゾチックな美しさは堪能したが、それ以上のものを読み取ることはできなかった。



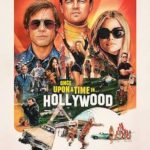

コメント