原作はルイザ・メイ・オルコットの『若草物語』。
監督は『レディ・バード』のグレタ・ガーウィグ。
原題は「Little Women」。
アカデミー賞では作品賞など6部門でノミネートされ、衣装デザイン賞を受賞した。
物語
マーチ家の次女・ジョー(シアーシャ・ローナン)は、ニューヨークで家庭教師をしつつ作家修行に励んでいる。
出版社にその作品が売れるようになって喜んだのもつかの間、故郷から手紙がやってくる。そこには三女ベスの具合がよくないという旨が書かれている。列車で故郷へ戻ることになったジョーは、マーチ家の四人の姉妹が揃って暮らしていた過去を思い出す。
数々の『若草物語』と新しい挑戦
この原作は何度も映画化されているようだ。それだけ『若草物語』が愛されている作品ということなのだろうと思うのだが、女性向けというイメージがあったからかまったく触れたことがなかった。その意味ではさほど期待もしていなかったのだが、ほのぼのしてとてもいい話だったし、また四姉妹を演じる女優陣の魅力もあって素直に満足のいく作品だったと思う。
本作は今になって古臭い作品を再映画化するというわけで、そのためには何らかの過去作品との差異を意識せざるを得ないと思う。その工夫のひとつは、本作が次女であり主人公となるジョーが、作家修行をしている「現在時」から「過去」を振り返るという形式になっているところだろう。そのため「現在」と「過去」を何度も行き来することになるのだが、この形式は最後になって活きてくる。
四姉妹のキャラ
長女メグを演じるのはエマ・ワトソン。メグは好きな男性とごく普通に結婚することを夢見るロマンチスト。しかし、愛情を選んだことにより、経済的には苦しむことになる。
次女ジョー役はシアーシャ・ローナン。男勝りで自立する女性になりたいジョーは、作家として自らの手で稼ぐことを目指すことになる。
三女ベス(エリザ・スカンレン)は、ピアノを弾くことが上手で、困っている人を放っておけないやさしさを持つ。しかし、病弱なところがあり、若くして亡くなることに(ベスのピアノのエピソードは泣かせる場面)。
四女エイミー(フローレンス・ピュー)は自由奔放な女性。ジョーとは対立するところがあり、ふたりの関係性も本作の重要なドラマとなっていく。また、エイミーが伯母(メリル・ストリープ)に気に入られているのは、「お金持ちと結婚する」というマーチ家を救う手段を理解しているから。フローレンス・ピューが演じるこの役は、一番のおいしい役どころともいえ、エイミーの無邪気さが本作の多幸感を担っているようにも感じられた。
そのほかではジョーにプロポーズすることになる、隣家のローリーを演じるのはティモシー・シャラメ。また、前半はずっと不在なのだが、マーチ家の父親を演じるのは『ブレイキング・バッド』で胡散臭い弁護士を演じていたボブ・オデンカークだったのも、『ブレイキング・バッド』を最近楽しんだ者としてはツボだった(こちらでは意外といい人に見える)。

『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』
他愛のない日常
主人公であるジョーが書く小説は軽い読み物の娯楽作らしく、ニューヨークで同じ家の家庭教師となっているベア(ルイ・ガレル)の評価からすると「がっかり」なものらしい。というのもジョーは金を稼ぐために書いているのであって、編集者が求めるものを書くようになっているからだろう。
その意味では本作で描かれる内容は、ジョーがニューヨークで書いていた娯楽作とは正反対の他愛のない日常が描かれている。四人姉妹と母親(ローラ・ダーン)とお手伝いという女性だらけの家は、それだけで騒々しい。父親は南北戦争の従軍牧師で不在なのだが、マーチ家は女性だらけでかえって落ち着かないんじゃないかと思えるほどだ。
そして、そんな女性陣の間で話題となるのは女性の幸せということになるだろう。ジョーは「結婚だけが女性の幸せなんてあり得ない」と考えるが、叔母は金持ちの男性と結婚することがマーチ家を救うことだという現実論を展開する。この時代の女性が外で働くことは難しく、結婚することが生きていく術だったからだ。それでも強情なジョーは、富豪でもあるローリーからプロポーズを受けつつも、それを断って独り立ちすることを望む(のちに後悔したりもするわけだが)。

『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』
構成の妙
特徴的なのが「現在」と「過去」を行き来する構成で、それは何度も繰り返されることになる。最初はちょっと混乱するかもしれないが、映像の上でも区別がつくように工夫がなされてもいる。色彩を抑えて冷たい印象なのが「現在」で、色合いが豊かで輝いて見えるのが「過去」の映像ということになる。
なぜ「過去」の映像が輝いて見えるのかと言えば、これはジョーが過去のことを美化しているからとも言える。ジョーは四人が揃っていた子供時代を黄金時代と感じていて、長女のメグが結婚していくことも裏切りのようにすら感じている。7年後の「現在」では四人姉妹が離ればなれになってしまっている状況からすれば、四人が揃っていた頃はかけがえのない時間で、その時代はジョーにとって光輝いて感じられるのだろう。
三女のベスの体調が思わしくないということが故郷へ戻るきっかけだが、ジョーはベスと一緒に穏やかな時間を過ごすものの、ベスは帰らぬ人となってしまう。そのことがジョーに出版社の求めるものとは異なる、自分の書きたいものを自由に書いた『若草物語』という自伝的小説を書かせることになる。
ジョーが『若草物語』という小説に記しているのは、四人が一緒に暮らしていた頃の話であり、それはジョーが「現在」から振り返っていた「過去」と重なってくる。この段階に至り、「現在」と「過去」という構図は、作家であるジョーが生きている「現実」と、そのジョーが創作した「フィクション」の関係にも見えるようになる(「過去」が美化されていたのは、そこにフィクションが混じっているからとも言える)。それまでは「現在」と「過去」の違いだったものが、メタフィクションと感じられるようになっていくのだ。

『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』
フィクションと現実
その小説のラストでは、ジョーはベアと結婚することになるわけだが、これは出版社の求めに応じて書かれたものだ。ジョーはフィクションの結末に関しては妥協したのだ。
ちなみに現実世界で『若草物語』の原作者となっているのはルイザ・メイ・オルコットだが、彼女は生涯結婚することがなかったのだという。ルイザ・メイ・オルコットは、自分をモデルにジョーというキャラを創造したわけだが、ラストの部分では現実における信念を曲げ、自分の分身たるジョーを結婚させたということになる。
自伝的というのはあくまでも自分がモデルという触れ込みであり、当然ながらフィクションは混じっているということだろう。ルイザ・メイ・オルコットの妹が若くして亡くなったことは事実らしいが、結婚に関してはフィクションを加えて小説化しているということだ。監督・脚本のグレタ・ガーウィグの前作『レディ・バード』も自伝的要素が入っているとのことで、そうした経験もあって本作が誕生したということなのかもしれない。
過去作品との差異
本作を観た後に、マーヴィン・ルロイ版の『若草物語』を観たのだが、これは原作に忠実に映画化されたものと思われ、ジョーはラストでベアと結婚したところで終わる。しかし、この展開だとどうしてジョーがローリーとの結婚を拒否したのかが腑に落ちない。単純にローリーのことが好きではなかっただけのようにも見えてしまうのだ。
マーヴィン・ルロイ版の『若草物語』では、原作者のルイザ・メイ・オルコットの本音と、フィクションである『若草物語』との間の差異には触れられていないわけで、観客としても「女性の幸せはやはり結婚にあるのだ」という従来の考えをなぞるだけになってしまうとも言える。
一方で本作『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』の場合は、ラストでジョー=ルイザ・メイ・オルコットの現実と、フィクションのなかのジョーの姿が曖昧のまま交じり合う形で進んでいく。この明確に分けられないのがうまいところで、ここではジョーの現実とフィクションのなかのジョーは区別できない。それによって結婚というハッピーエンドの歓喜と、フィクション内部における妥協のどちらも感じさせるという離れ技を達成しているのだ。
さらに、「現在時」のジョーは出版社と対等にやり取りするほどに聡い女性で、自分の作品が守られるような権利を主張していくことになる。男性が優位となっている社会において、自立する女性として生きているわけだ。あまり説教臭くならない程度のフェミニズムと、観客が望むであろうハッピーエンドの、そのどちらをも実現してしまったようにも感じられるラストは見事だったと思う。





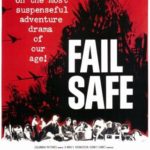
コメント